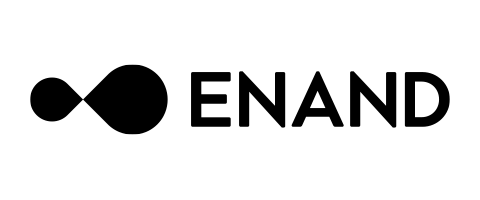石坂産業訪問勉強会レポート
ゴミをゴミにしない挑戦 ─ 持続可能な経営の本質を学ぶ一日

イントロダクション
世界55カ国、年間6万人が訪れる埼玉・三芳町の石坂産業。 「ゴミをゴミにしない社会」を掲げ、再資源化率98%を誇る環境創造企業です。 2025年10月24日、現地にて訪問勉強会を開催しました。 工場見学、社員セッション、そして森の散策を通して、循環型経営の現場から多くの学びを得ました。
当日のスケジュール
| 10:00 | 集合(くぬぎの森交流プラザ) |
|---|---|
| 10:30 | オリエンテーション |
| 11:00 | 資源再生工場見学 |
| 12:00 | 里山見学・質疑応答 |
| 13:00 | 発酵弁当ランチ |
| 14:00 | 社員セッション |
| 15:30 | 終了(現地解散) |
現地レポート
オリエンテーション:「ゴミをゴミにしない社会」へ
石坂産業は、産業廃棄物の再資源化率98%を誇る環境創造企業。 1999年のダイオキシン報道という逆境を経て、「脱・産廃屋」を掲げた改革が始まりました。 約2億円を投じた見学通路の整備により、工場を「地域に開く」ことで信頼を取り戻し、 いまでは年間6万人が訪れる“見せる経営”の象徴となっています。

資源再生工場見学:見せる経営の現場
廃材がベルトコンベアを流れ、瞬く間に資源へと分けられていく光景。 「ゴミを減らす」のではなく「資源を増やす」という逆転の発想が印象的でした。




里山再生プロジェクト:森が語る循環
不法投棄の森を再生し、地域と共に守る「くぬぎの森」。 東京ドーム4個分の敷地を保全し、JHEP認証の最高ランク「AAA」を取得。 子どもたちが自然に触れ、地域が誇る“学びの森”として息づいています。


発酵弁当:食の循環を味わう
自社農園「石坂オーガニックファーム」で育てた野菜を使った発酵弁当。 「土からはじまる循環」を五感で体感しました。

社員セッション:理念を自分の言葉で語る人たち
部署も国籍も異なる3名の社員が、それぞれの視点で仕事を語りました。 「誰かに言われたからではなく、自分がやりたいからやる」── その姿勢こそ、持続可能な組織の原動力でした。



参加者の声
理念がすみずみにまで浸透しており、社員一人ひとりが自分の言葉で会社を語っていたことに感動しました。
社員教育の徹底ぶりが印象的でした。入社数年の若手が会社のビジョンを堂々と説明できる姿に驚きました。
地域との共生をミッションとするなら、財務的課題よりも理念を優先する。その姿勢を実際に見せていただき、経営の本質を感じました。
「見せる経営」という言葉の意味を体感しました。透明性のある経営は、信頼そのものを生み出している。
創業者のスピリッツが、社長、社員へと確実に受け継がれている。組織文化の強さを目の当たりにしました。
工場も森も整然としていて、美しさそのものが理念を物語っていました。経営とデザインが一致していると感じました。
若手社員が主体的に動き、上司がそれを信じて任せている。まさに「自走する組織」だと感じました。
同業種ではない私たちにも通じる学びが多く、理念経営の重要性を再確認しました。
理想を掲げるだけでなく、それを仕組みと文化に落とし込むことの大切さを実感しました。
まとめ ― 三つの学びの軸
1. 理想を求める力
石坂産業の現場では、入社年次の浅いスタッフでさえ自然に理念を語る姿が見られた。 それは、ビジョンが単なる言葉ではなく、日常の意思決定や行動の基準として可視化されているからだ。 再資源化率98%という数字のさらに先、残る2%を突き詰めようとするその姿勢は「理想を追う力」そのもの。 それは企業の枠を超え、人類全体が共有すべき目標でもある。 ロゴの“100度”という角度にまで理念を込める――その徹底が文化をつくっていた。
2. 付加価値の源泉
石坂産業には「分別」「分級」など、“分ける”ことを大切にする文化がある。 言葉を細やかに分けるということは、それぞれに意味を見いだしているということだ。 分ければ分けるほど価値が高まる。 この考え方は、税理士が行う仕訳や分類にも通じる。 情報や事象を丁寧に仕分け、分類することで、そこに新しい価値が生まれる可能性があるのだ。
3. “強み”という共通言語
石坂産業では、ストレングスファインダーを通して「強みを意識する文化」が根づいている。 共通の言葉が流通している組織は、コミュニケーションロスが少ない。 さらに近年は、優秀な若手社員が次々と入社している。 彼らは「環境問題」という共通の危機意識を持ち、その思いを共有できる場として石坂産業を選んでいる。 共通の関心領域があること――それが、組織の基盤を盤石にする最大の強みである。
理想を追い、価値を見いだし、強みでつながる。 この三つの軸は、石坂産業の持続可能な経営を支える普遍的な原理であり、 これからの時代を生きる私たち自身への問いかけでもある。